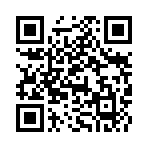2009年10月21日
2009年06月17日
不動産情報 行橋市
所在地:福岡県行橋市金屋
土地面積:78.45坪
交通:西鉄バス 常盤橋バス停 徒歩3分
用途地域:無指定
地目:宅地
建蔽率:70%
容積率:300%
上水道:市営水道
ガス:LPG集中方式
下水道:浄化槽による水洗
校区:今元小学校・今元中学校区
形態:仲介
販売価格:580万円 (相談承ります)
2009年06月04日
不動産情報 八幡東区 <お知らせ>
以前からご紹介させていただいておりました八幡東区山路松尾町の借家ですが
おかげさまで成約となりましたのでお知らせいたします。
ありがとうございました
物件詳細:http://yokomizo.yoka-yoka.jp/e232328.html
おかげさまで成約となりましたのでお知らせいたします。
ありがとうございました

物件詳細:http://yokomizo.yoka-yoka.jp/e232328.html
2009年04月30日
不動産情報 八幡東区 <お知らせ>
以前からご紹介させていただいておりました八幡東区祝町二丁目の売地ですが
おかげさまで成約となりましたのでお知らせいたします。
ありがとうございました
物件詳細:http://yokomizo.yoka-yoka.jp/e110706.html
おかげさまで成約となりましたのでお知らせいたします。
ありがとうございました

物件詳細:http://yokomizo.yoka-yoka.jp/e110706.html
2009年04月18日
不動産情報 八幡東区 借家

北九州市八幡東区山路松尾町 一戸建て借家
●間取り/6DK
●西鉄バス 八幡高校下バス停 徒歩3分
●月額賃料/6.5万円 ●礼金/2ヶ月 ●管理費/なし
●駐車場/有り(無料) ●仲介
一部リフォーム済
外犬可、槻田小学校600m
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
2008年08月01日
不動産業 アレコレ話
瑕疵担保責任の話
中古住宅の購入の契約をしてすぐにシロアリの発生を確認した場合。
まだ住んではいないけど、すでに契約はすんでいるけど、どうしたらいいのか・・・
これは瑕疵担保責任といい、売主の責任になります。
瑕疵担保責任とは、購入前からの欠陥品について売主の負う責任のことです。
たとえ売主がその欠陥のことを知らなかったり、また責任がない場合でも担保責任を負うことになります。
詳しく書くとかなり難しくなりますので、『シロアリがいた』という例で、具体的にまとめてみます。
☆どんな時に瑕疵担保責任が認められるのか?
・隠れた瑕疵であり、契約時にはその欠陥が存在していた場合
シロアリが屋根裏にいた場合、買主は契約前にその欠陥を発見することは困難です。
更にそのシロアリが契約時にすでに発生していた場合は瑕疵担保責任が認められます。
☆瑕疵担保責任の効果とは
・欠陥の存在を知らずに契約した買主は、売主に対して損害賠償を請求することができます。
シロアリがいることを知らなかった買主は、売主に損害賠償請求できるのです。
・場合によっては契約解除ができます 。
シロアリ被害で屋根裏の柱がボロボロ。
そのままでは安全に暮らすことができない場合は契約解除が可能です。
ただし、シロアリの存在を知っていた買主は、契約解除はできません。
☆請求できるのはいつまでか?
・その事実を知った時から1年
シロアリの存在を知ってから1年以内です。
これは契約の解除及び損害賠償請求共にです。
シロアリ以外でも、契約前に発見することができない欠陥については認められます。
ただし、あくまでもその存在を知らなかった買主だけであり、知っていた場合はいかなる主張もできません。
また欠陥がある=契約解除ではありませんので、不動産を購入する際は、細心の注意を払うことが大切になってきます。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします


中古住宅の購入の契約をしてすぐにシロアリの発生を確認した場合。
まだ住んではいないけど、すでに契約はすんでいるけど、どうしたらいいのか・・・
これは瑕疵担保責任といい、売主の責任になります。
瑕疵担保責任とは、購入前からの欠陥品について売主の負う責任のことです。
たとえ売主がその欠陥のことを知らなかったり、また責任がない場合でも担保責任を負うことになります。
詳しく書くとかなり難しくなりますので、『シロアリがいた』という例で、具体的にまとめてみます。
☆どんな時に瑕疵担保責任が認められるのか?
・隠れた瑕疵であり、契約時にはその欠陥が存在していた場合
シロアリが屋根裏にいた場合、買主は契約前にその欠陥を発見することは困難です。
更にそのシロアリが契約時にすでに発生していた場合は瑕疵担保責任が認められます。
☆瑕疵担保責任の効果とは
・欠陥の存在を知らずに契約した買主は、売主に対して損害賠償を請求することができます。
シロアリがいることを知らなかった買主は、売主に損害賠償請求できるのです。
・場合によっては契約解除ができます 。
シロアリ被害で屋根裏の柱がボロボロ。
そのままでは安全に暮らすことができない場合は契約解除が可能です。
ただし、シロアリの存在を知っていた買主は、契約解除はできません。
☆請求できるのはいつまでか?
・その事実を知った時から1年
シロアリの存在を知ってから1年以内です。
これは契約の解除及び損害賠償請求共にです。
シロアリ以外でも、契約前に発見することができない欠陥については認められます。
ただし、あくまでもその存在を知らなかった買主だけであり、知っていた場合はいかなる主張もできません。
また欠陥がある=契約解除ではありませんので、不動産を購入する際は、細心の注意を払うことが大切になってきます。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします
タグ :不動産マメ知識
2008年07月23日
不動産情報 八幡東区
所在地:福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目
土地面積(公募面積):217.94㎡(66.04坪)
交通:西鉄バス 四条橋バス停 徒歩2分
用途地域:住居地域(調査中)
地目:宅地
建蔽率:60%
容積率:200%
設備:都市ガス 電気 上水道 下水道
接道状況:西側3.0m公道に12m接道
現状:更地
形態:仲介
販売価格:1,650万円
※建築条件付になります。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします
2008年07月20日
不動産業 アレコレ話
土地境界の話
なぜ境界に関するトラブルが発生するのか??
境界は、非常にもめやすく、トラブルの種であることは、皆さんも感じていらっしゃるのではないでしょうか。
では、なぜ境界がもめやすいのかを整理しておきます。
①公図のあいまいさ
不動産登記法が改正されるまでは、旧土地台帳法が存在し、登記制度とは別に不動産の事実状態を把握することを目的とした土地台帳制度がありました。
土地の区画と地番づけは、測量技術が乏しい時代に作成しており、これが法務局にある公図へとつながっています。
そのため公図の多くは、不動産登記法17条の土地及び地番を明確にする地図に準ずる図面として位置づけられています。
もし公図の土地の位置が現物と異なる場合や、公図に該当する土地の記載がないなどの場合は、所有者やその他の利害関係人は、土地所在図、地積測量図を添付のうえ、その訂正の申し出をすることができます。
それを受けて登記官は、実地に調査し、公図に誤りがあれば、職権で訂正します。
②境界は目に見えない
境界は、直接には目に見えません。
このためお互いが勝手なことを主張しあう原因になったり、また自分の主張の誤りに気づくことなく、自分は正当であると考えたりすることがトラブルの原因にもなっています。
また逆に直接目に見えないために、目に見えるものを盲信しがちなこともトラブル原因の一つです。
例えば、境界石らしき物が見つかると、たとえそれが動いていたとしても、それを絶対視してしまうなどです。
③土地へのこだわり
土地が高騰化し、かなりの価値をあわらしていることもトラブルの大きな原因です。
譲っても惜しくないような安いものなら、さほどトラブルにはならないのですが、10cmでもかなり大きな資産になります。
このように土地は高額な資産でもあるわけですし、先祖から所有している、というような思い入れなどの理由も加わり、問題が複雑化していることもトラブルを助長させる側面でもあるのです。
≪トラブル予防方法≫
一番の問題はやはり「目に見えない事によるあいまいさ」ではないでしょうか。
このあいまいさを取り除くことがトラブル予防になると考えられます。
境界については、①でもわかるように、出発点からあいまいであることが理解できると思います。
このようなあいまいさが特質の境界を考えると、境界が紛争やトラブルの火種であることはむしろ当然ともいえます。
「なんとなく境界はこれだと思っている」とか「境界は親から聞いている」、「売主からそのように説明をうけた」など不確定要素が強く、それは自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。
これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。
このあいまいさを払拭するのです。
そのため隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置してはいかがでしょうか。
もちろんこれだけでは、公的に境界がそこに定まるわけではありませんので、将来紛争が起こる心配があります。
最終的には、境界確定の訴訟をして境界を定めておくといいと思います。
もし、隣家と訴訟までしなくたいというのなら(多くの方がそう思っているのではないでしょうか)、話し合いや立会いで私的の意味でも境界を決めておけばいいと思います。
そして決めた境界に境界標を設置し、取り決めした内容を文書など形に残るもので保存しておきます。
それだけでもお互いに無用な主張はしなくなりますし、第三者もいちおうそこが境界であるとの前提で行動し、事態は落ち着きますから、実際上の効果は十分な場合が多いと思います。
境界のトラブルは事態が起こってからでは、当時取り決めした人が亡くなっていてわからないなどの理由により大きな問題に発展することが多くありますので、紛争がおこる前から事前の予防として対策を講じておく必要があります。
そして近隣の方々との良い近所付き合いを続けていただければ幸いです。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします


なぜ境界に関するトラブルが発生するのか??
境界は、非常にもめやすく、トラブルの種であることは、皆さんも感じていらっしゃるのではないでしょうか。
では、なぜ境界がもめやすいのかを整理しておきます。
①公図のあいまいさ
不動産登記法が改正されるまでは、旧土地台帳法が存在し、登記制度とは別に不動産の事実状態を把握することを目的とした土地台帳制度がありました。
土地の区画と地番づけは、測量技術が乏しい時代に作成しており、これが法務局にある公図へとつながっています。
そのため公図の多くは、不動産登記法17条の土地及び地番を明確にする地図に準ずる図面として位置づけられています。
もし公図の土地の位置が現物と異なる場合や、公図に該当する土地の記載がないなどの場合は、所有者やその他の利害関係人は、土地所在図、地積測量図を添付のうえ、その訂正の申し出をすることができます。
それを受けて登記官は、実地に調査し、公図に誤りがあれば、職権で訂正します。
②境界は目に見えない
境界は、直接には目に見えません。
このためお互いが勝手なことを主張しあう原因になったり、また自分の主張の誤りに気づくことなく、自分は正当であると考えたりすることがトラブルの原因にもなっています。
また逆に直接目に見えないために、目に見えるものを盲信しがちなこともトラブル原因の一つです。
例えば、境界石らしき物が見つかると、たとえそれが動いていたとしても、それを絶対視してしまうなどです。
③土地へのこだわり
土地が高騰化し、かなりの価値をあわらしていることもトラブルの大きな原因です。
譲っても惜しくないような安いものなら、さほどトラブルにはならないのですが、10cmでもかなり大きな資産になります。
このように土地は高額な資産でもあるわけですし、先祖から所有している、というような思い入れなどの理由も加わり、問題が複雑化していることもトラブルを助長させる側面でもあるのです。
≪トラブル予防方法≫
一番の問題はやはり「目に見えない事によるあいまいさ」ではないでしょうか。
このあいまいさを取り除くことがトラブル予防になると考えられます。
境界については、①でもわかるように、出発点からあいまいであることが理解できると思います。
このようなあいまいさが特質の境界を考えると、境界が紛争やトラブルの火種であることはむしろ当然ともいえます。
「なんとなく境界はこれだと思っている」とか「境界は親から聞いている」、「売主からそのように説明をうけた」など不確定要素が強く、それは自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。
これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。
このあいまいさを払拭するのです。
そのため隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置してはいかがでしょうか。
もちろんこれだけでは、公的に境界がそこに定まるわけではありませんので、将来紛争が起こる心配があります。
最終的には、境界確定の訴訟をして境界を定めておくといいと思います。
もし、隣家と訴訟までしなくたいというのなら(多くの方がそう思っているのではないでしょうか)、話し合いや立会いで私的の意味でも境界を決めておけばいいと思います。
そして決めた境界に境界標を設置し、取り決めした内容を文書など形に残るもので保存しておきます。
それだけでもお互いに無用な主張はしなくなりますし、第三者もいちおうそこが境界であるとの前提で行動し、事態は落ち着きますから、実際上の効果は十分な場合が多いと思います。
境界のトラブルは事態が起こってからでは、当時取り決めした人が亡くなっていてわからないなどの理由により大きな問題に発展することが多くありますので、紛争がおこる前から事前の予防として対策を講じておく必要があります。
そして近隣の方々との良い近所付き合いを続けていただければ幸いです。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします
2008年07月05日
不動産業 アレコレ話
土地の価格の話
今あなたが欲しいと思っている土地の価格が適正かどうかを判断することは非常に重要なことです。
土地の価格には、公示価格、路線価、基準地価等がありますが、それらがどのような意味をもつ価格かを知っていますか?
適正価格かどうかを判断する参考として、いろいろな価格がどういうものかを調べてみました。
土地を評価するのに、次の5つの価格を用います。
① 公示地価:国土庁が毎年1月1日の値段を調べ3月に発表。
地価公示によって評価された価格を公示地価といいます。
最も代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表しています。
地価公示では全国で選定された3万数千地点の都市計画区域内の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、公示しています。
公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。
② 基準地価:都道府県が毎年7月1日の値段を調べ9月に発表。公示地価の足りないところを補う価格です。
公示地価と同様に、住宅地、商業地、工業地などの用途地域ごとに、各地区の基準地が選ばれ、1㎡当たり単価で表示されます。
標準地の正常な価格で、一般の土地取引の指標となります。
市町村役場に備えてありますから、いつでも閲覧できます。
③ 路線価:国税庁が毎年1月1日の値段を調べ8月に発表。
相続税や贈与税を計算するときの地価で、公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価しています。
都市部などにある主要な道路に面した土地の税務上の評価額を、1㎡当たりの単価で表示されます。
全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図を閲覧できます。
宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。
④ 固定資産評価額:市町村がすべての土地について定めている価格。
固定資産税評価額とは固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。
土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」といいます。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則です。
ただし分筆・合筆・地目変更により土地の区画・形質が変化したり、著しい地価の下落があったなどの事情があるときは、基準年度以外の年度であっても、土地の固定資産税評価額を変更するものとされています。
⑤ 実勢価格:実際に売り買いされている価格。(時価ともいいます)
その土地のその時点における相場に従った価格ということになります。
調査の方法としては、不動産鑑定士に鑑定してもらうこともできますが、不動産情報誌や新聞の折込広告なども参考になります。
また、売買予定地域の業者に聞いてみるのも有効です。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします


今あなたが欲しいと思っている土地の価格が適正かどうかを判断することは非常に重要なことです。
土地の価格には、公示価格、路線価、基準地価等がありますが、それらがどのような意味をもつ価格かを知っていますか?
適正価格かどうかを判断する参考として、いろいろな価格がどういうものかを調べてみました。
土地を評価するのに、次の5つの価格を用います。
① 公示地価:国土庁が毎年1月1日の値段を調べ3月に発表。
地価公示によって評価された価格を公示地価といいます。
最も代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表しています。
地価公示では全国で選定された3万数千地点の都市計画区域内の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、公示しています。
公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。
② 基準地価:都道府県が毎年7月1日の値段を調べ9月に発表。公示地価の足りないところを補う価格です。
公示地価と同様に、住宅地、商業地、工業地などの用途地域ごとに、各地区の基準地が選ばれ、1㎡当たり単価で表示されます。
標準地の正常な価格で、一般の土地取引の指標となります。
市町村役場に備えてありますから、いつでも閲覧できます。
③ 路線価:国税庁が毎年1月1日の値段を調べ8月に発表。
相続税や贈与税を計算するときの地価で、公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価しています。
都市部などにある主要な道路に面した土地の税務上の評価額を、1㎡当たりの単価で表示されます。
全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図を閲覧できます。
宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。
④ 固定資産評価額:市町村がすべての土地について定めている価格。
固定資産税評価額とは固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。
土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」といいます。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則です。
ただし分筆・合筆・地目変更により土地の区画・形質が変化したり、著しい地価の下落があったなどの事情があるときは、基準年度以外の年度であっても、土地の固定資産税評価額を変更するものとされています。
⑤ 実勢価格:実際に売り買いされている価格。(時価ともいいます)
その土地のその時点における相場に従った価格ということになります。
調査の方法としては、不動産鑑定士に鑑定してもらうこともできますが、不動産情報誌や新聞の折込広告なども参考になります。
また、売買予定地域の業者に聞いてみるのも有効です。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします
タグ :不動産マメ知識
2008年06月25日
不動産業 アレコレ話
不動産を取得したときの税金の話
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、以下のような税金がかかります。
①住宅取得資金の贈与を受けたとき→贈与税(国税)
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象となります。
②契約書を交わすとき→印紙税(国税)
売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。
③登記するとき→登録免許税(国税)
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。
④取得したあとで→不動産取得税(地方税)
土地や住宅を買ったり、住宅を新築・増改築したときには、不動産取得税の対象となります。
⑤所得税の確定申告のとき→所得税の住宅ローン控除(国税)
税金は納めるのが通例ですが、中にはもどってくるものもあります。
それが住宅ローン控除という取得税の特別控除です。
⑥相続したとき→相続税(国税)
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。
これらの税金については、特定の場合には税金が軽減されます。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします


土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、以下のような税金がかかります。
①住宅取得資金の贈与を受けたとき→贈与税(国税)
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象となります。
②契約書を交わすとき→印紙税(国税)
売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。
③登記するとき→登録免許税(国税)
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。
④取得したあとで→不動産取得税(地方税)
土地や住宅を買ったり、住宅を新築・増改築したときには、不動産取得税の対象となります。
⑤所得税の確定申告のとき→所得税の住宅ローン控除(国税)
税金は納めるのが通例ですが、中にはもどってくるものもあります。
それが住宅ローン控除という取得税の特別控除です。
⑥相続したとき→相続税(国税)
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。
これらの税金については、特定の場合には税金が軽減されます。
国内最大級の物件数!信頼の情報!不動産のことならHOME'Sへ
大手・厳選会社へ一括見積りで最大50%OFF!
今日もポチっとお願いします
タグ :不動産マメ知識